| 記事の要旨 | 英文(ChatGPT) |
| -受験者の技術や対策が進化するにつれ、全体の合格率が20%に近づくという大数の法則を、コロコロ2割と呼びます。 -データドリブンの議論を進めるために、データを分析し、仮説を立てることが重要です。 -この記事の表から、1次の申込数の増加、1次合格率の上昇、2次受験者数増加といった変化が読み取れます。 -2次試験の申込平均と合格平均年齢に大きな差があります。これは高年齢の受験者が翌年再受験することで、不合格者の平均年齢が上昇していることを示しています。 -2次試験に合格するための具体的な対策として、情報処理能力の向上、問題解決力や発想力の養成、未知の問題への対応力の養成が挙げられます。 | -The transcript discusses the "law of logarithmic distribution," which refers to the phenomenon where the overall pass rate converges to 20% as exam techniques and strategies improve. -The importance of analyzing data and making hypotheses based on data before discussing the aforementioned phenomenon is emphasized. -The key information that can be gleaned from the analyzed data is presented in three points: an increase in the number of applicants for the first-stage exam, an increase in the pass rate for the first-stage exam, and an increase in the number of candidates for the second-stage exam. -The average age of applicants and successful candidates in the first and second-stage exams is analyzed, revealing a significant deviation between the average ages of applicants and successful candidates in the second-stage exam. -Specific strategies are suggested for passing the second-stage exam, such as developing information processing skills, problem-solving and creative thinking abilities, and the ability to handle unfamiliar problems. |
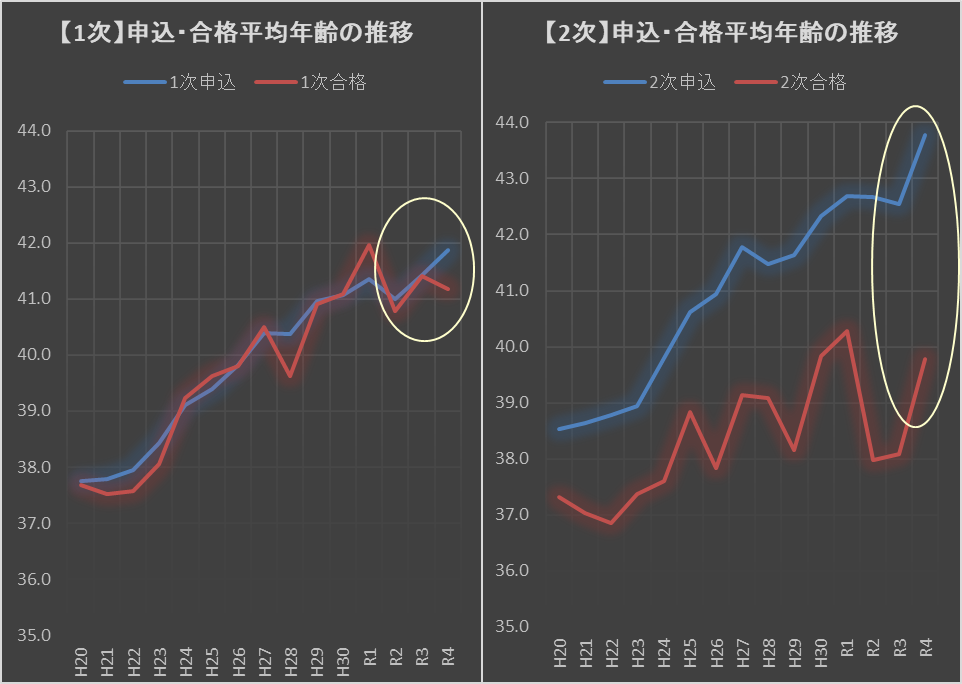
1次試験が申込=合格平均年齢であるのに対し、2次試験は申込⇔合格平均年齢に大きな乖離があります。この数値を以下のように分析します。
1次試験の申込年齢と合格年齢は、年々上昇傾向にあります。この傾向は、社会人が資格取得に積極的に取り組んでいることや、高齢化社会に伴う働き方改革などが背景にあると考えられます。例えば、2022年における申込年齢は41.9歳で、合格年齢は41.2歳となっており、申込年齢は2008年から14年間で4.2歳、合格年齢は同じ期間で3.5歳も上昇しています。
2次試験の合格年齢は1次試験よりも若干低い傾向にあり、この差は比較的小さいものの、年々少しずつ拡大しています。例えば、2022年における申込年齢は43.8歳で、合格年齢は39.8歳となっており、申込年齢が2008年から14年間で5.3歳上昇したのに対し、合格年齢は同じ期間で2.5歳の上昇にとどまっています。
2次合格者の申込年齢と合格年齢を見ると、大きな差異が見られます。特に、2次試験の申込年齢が比較的高齢であるにもかかわらず、合格年齢は比較的若年層に集中していることがわかります。これは、デジタル社会の浸透により大量の情報を素早く処理する能力を問う傾向が強まったことが原因と考えられます。従来の経験に依存する高齢層が、新しい情報処理能力を必要とする試験に合格しにくくなったため、合格者の年齢層が若年層に偏っていると考えられます。
【データドリブン~ファクトベースの第一歩】
①2次申込⇔合格平均年齢の差が大きいと気づく
②2次年齢別合格率が高齢者ほど低いと思い出す
③諦めず受け続ける高齢ベテ→申込高齢化の原因
④頭の固いおベテの同友館ヨイショの真逆を選ぶ
このサイトは同友館ヨイショの悪文をたびたび引用。そして、&ヘタクソ国語&同友館のベテノウハウを、一石二鳥で一掃な。
【表も読み取るGPT】合格数・率推移 / 平均年齢推移 / 地区別採用数・率推移
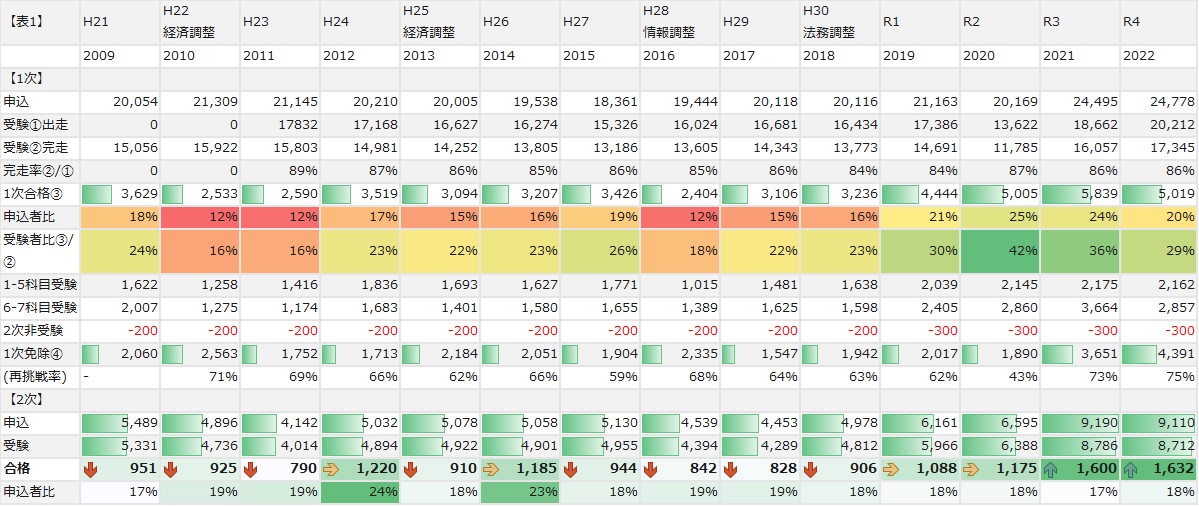
はい。では最初に、国家試験の申込~合格者数データを分析するときの留意点3つを、以下に紹介します。
受験者数や合格者数の単なる増減だけでなく、それに対する背景要因を分析することが重要です。例えば、診断士試験の1次受験者数が増加している理由については、資格の魅力UPや2次合格者数増による受かりやすくなったことが考えられます。このような背景を把握することで、数値だけでは分からない試験のトレンドを理解することができます。
合格率の変化を分析することが重要です。例えば、診断士試験の1次試験合格率が上昇しているのは、受験数と合格者数を狙った意図的なものという背景があります。このような背景を把握することで、単に数値が上昇しているだけでなく、試験の難易度が変化している可能性があることにも注意が必要です。
試験の内容や形式の変更点も分析することが重要です。例えば、診断士試験の2次試験受験者数が増加している理由については、筆記試験の採点技術が向上して、採点枚数による受験者数の上限を撤廃したためという背景があります。このような変更点を理解することで、試験の変化に対応した対策が必要であることにも気づくことができます。
はい、この表から読み取れる重要な情報は以下の3つです。これらの変化を踏まえて対策を取ることで、試験の合格率が高まる可能性があります。
1次試験申込数は、2010年から2022年にかけて総じて増加傾向にあります。特に2014年以降は、20,000人台前半を推移しています。一方、1次試験の合格率は、2010年から2018年まで約10%前後を推移していましたが、2019年以降は徐々に上昇し、2021年には14.3%となっています。また、1次試験の合格者数も、2010年から2022年にかけて増加傾向にあり、特に2019年以降は大幅に増加しています。
1次試験は2020年度から2021年度にかけて大幅に上昇しました。これは、2020年度に新型コロナウイルスの影響で試験が中止になったため、2021年度は受験者が前年度に比べて少なかったことや、試験の難易度が抑えられたことによるものと考えられます。しかし、2022年度には再び合格率が低下したため、2021年度は一時的なものだった可能性もあります。
2次試験受験者数は、2019年度から2022年度にかけて増加しています。これは、筆記試験の採点技術が向上して、採点枚数による受験者数の上限が撤廃されたことによるものと考えられます。また、1次合格者数が増加したことで2次試験を受験する人が増えた可能性もあります。ただし、2次試験の合格率はあまり変化しておらず、受験者数増加による難易度の変化は少ないと考えられます。
これらの要因を踏まえ、2次試験に合格するための具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。
情報収集・整理・分析のスキルを身につけることや、スピードを意識した練習を行うことが重要です。
試験ではなく実在企業の課題解決を検討することや、自分なりの考え方やアイデアを生かした回答を書くことが有効です。
想像力を働かせたり、さまざまな分野の情報を収集することが重要です。また、過去の問題に囚われず、より現実に即した問題や状況を想定することも必要です。
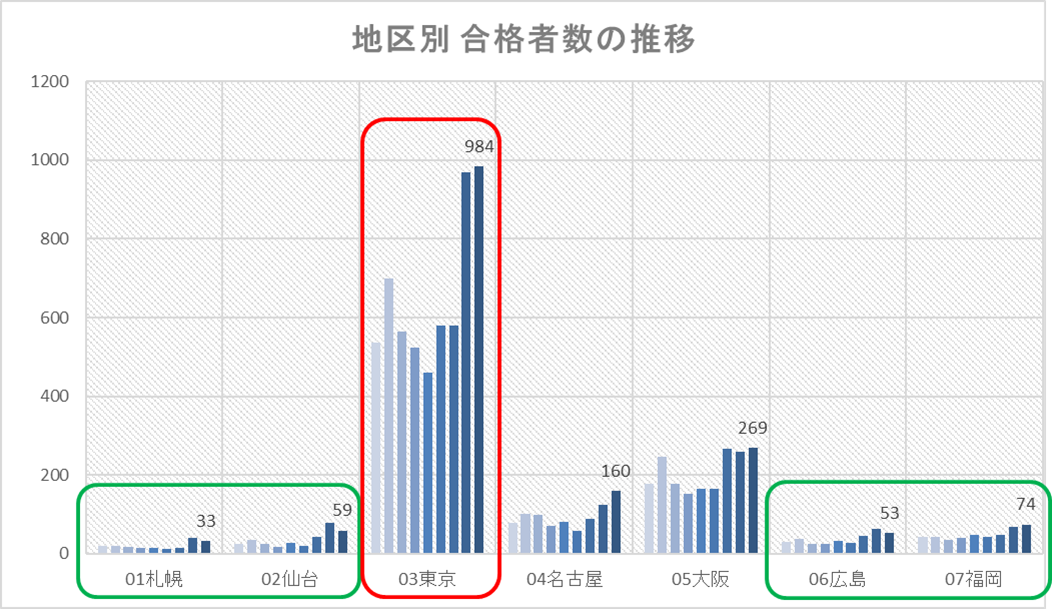
はい、中小企業診断士試験において、地方の合格数を増やすためには以下のような施策が考えられます。
東京や大阪の試験会場は多数存在しますが、地方における試験会場は限られています。地方においても試験会場を増設し、受験しやすい環境を整えることが必要です。
地方の受験者に対して、受験に必要な費用を補助する制度の整備や、受験に必要な情報提供・サポートを行う支援策の拡充が必要です。
地方企業との連携により、地方の実情に合わせた事例や問題を作成することで、地方の受験者が試験に臨む際に、より身近な問題に取り組めるようになります。また、地方企業との連携により、試験合格後に地方企業での就職や起業が促進され、地方経済の活性化につながることが期待されます。
地方試験会場の増設、地域企業で作問するなど、ははーんと頷く施策がズラリ。そしてGPT様が本気を出すと、秋の新作試験をズバリ的中させる予感しかしません。
今日のまとめ
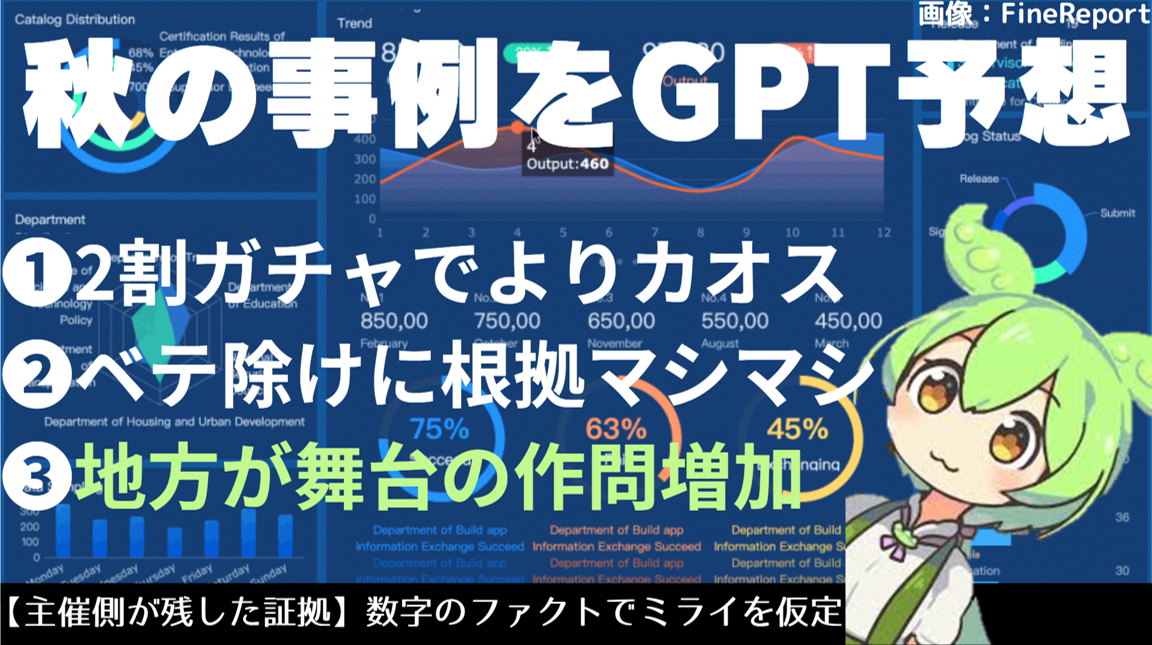
でもそこで中小企業白書を覚えたがるおベテはウンコ。このクソガチャ試験をさっさと当てるには、答を覚える間抜け勉強を止め、大量情報を処理する頭の回転を速める一択です。

