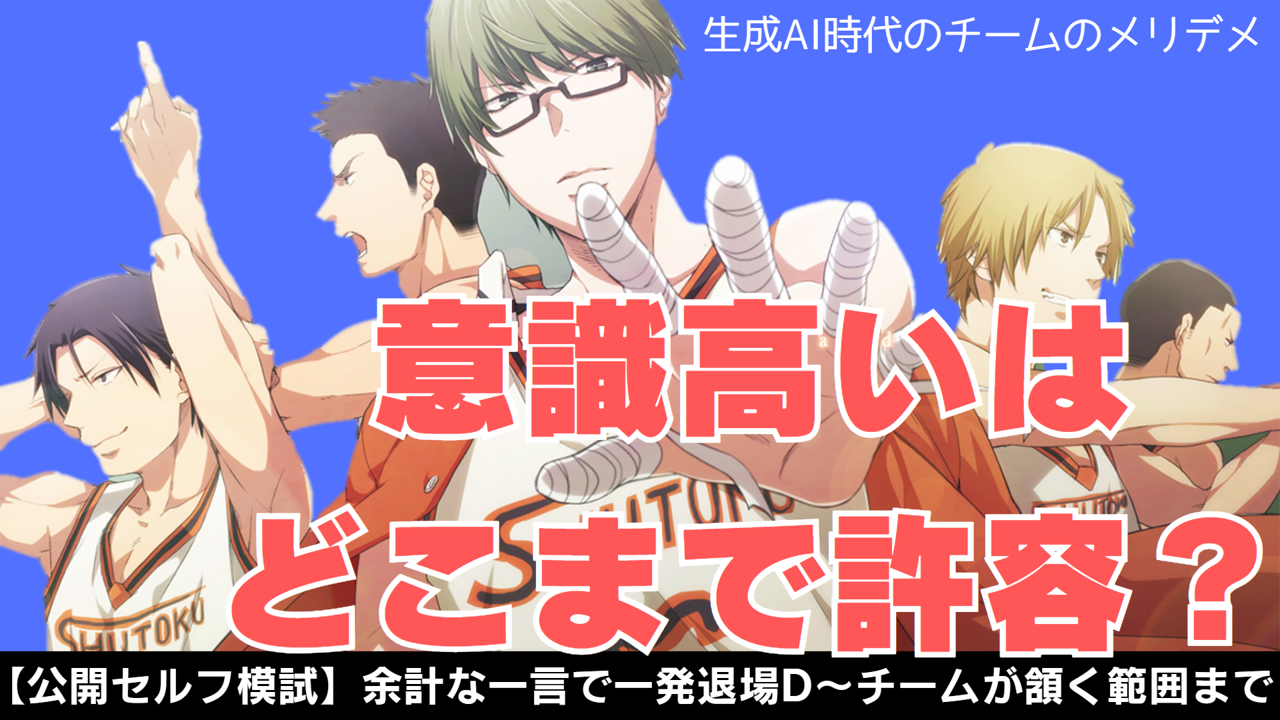
動画に生成AIとデジタルだらけの今年は、前年ふぞろい以上の答案を猫でも一瞬で書けてしまう。そこで【書きすぎ一発退場D】のリスクをみんなで学びます。
日頃から生成AIを使う方なら、隣より一段、二段階上の【意識高い答案】を自然に書ける。ところが良い意味で意識が高くても、周囲に悪影響を与えることがあります。
| 良い意味で意識が高い | 悪い意味で意識が高い | |
|---|---|---|
| メリット | ○○ 自己成長や目標達成に向けた積極性があり、周囲に良い影響を与える。社会貢献や協力を大切にし、チームプレイが得意。 | ×○ よくも悪くも自己主張が強く、目立ちたがり屋。自信を持ち、独立心が強い。 |
| デメリット | ○× 過度な自己要求でストレスを感じやすく、他人にも同じ要求を押し付けがち。過剰な競争心が人間関係に悪影響する。 | ×× 傲慢で他人を見下し、協力を妨げる。過度な競争心が他人との関係を悪化させ、孤立を招く。 |
当試験は多様性を重視するので、特定のやり方を押し付ける行為は嫌われる。そこで当サイトは最初からベテふぞ同友館の完全排除を申し渡し済です。
【公開セルフ模試】一発退場D回避 / 意識高いはどこまで許容?

診断士=難関資格!とは出版D社が合格目的マジョリティ相手に作り上げたデマそのもの。そこそこ企業のビジネスパーソンなら以下の通りあっさり解けます。
①初期の動画が一番正解
ここのサイトのように生成AIを使ってゴミ情報をバラまく行為が好ましいとは言えませんが、ベテふぞの余計なノウハウを黙らせる効果は見逃せません。
初期のYouTube動画では、診断士2次試験の基本的な戦略や勉強法が説明されます。例えば、過去問題を解く重要性や時間配分のコツが詳しく伝えられ、これらの基本戦略がほぼ網羅されます。
そして視聴者数を増やすべく、一部のクリエイターは本来必要な情報以上のことを提供し始めます。例えば、試験外のトピックや視聴者を引き込むための劇的な演出が増え、情報が複雑になり、本質的な情報が埋もれがちになります。
多くのクリエイターが同じ視聴者層に情報を提供しようとするほど、同じネタが繰り返されるループが起きます。例えば、特定の勉強法や過去問の解き方が何度も繰り返し紹介され、視聴者は飽きてしまい、視聴数が減少します。視聴者が求める情報の多様性が失われ始めているのです。
②事例Ⅱのカモの捕まえ方は丸裸
上品な生成AIが道端ウンコなる表現を使うことは決してありませんが、今の事例Ⅱはノロマが80分で解けないだけで、超イージーであるのは事実です。
ビジネスパーソンにとって、コトラーのマーケ4.0および5.0のコンセプトは、ビジネス環境のデジタル化に伴いますます重要性を増しています。この普及の過程は以下で説明できます。
- デジタル革命の影響: デジタル技術の急速な発展により、ビジネス環境が大きく変わり、これに適応するためにコトラーのマーケティングコンセプトがますます注目されるようになりました。
- 競争の激化: 企業間の競争が激しさを増し、顧客獲得と維持の難しさが増す中、コトラーのコンセプトに基づいた行動が、取引相手に受け入れ易いことも広く知られるようになりました。
- 成功事例の増加: マーケティング4.0および5.0のアプローチを取り入れた企業の成功事例がネットや動画で広まり、ネットワーク外部性のように同じ手口を採用する企業が増えました。
デジタルマーケティングの進歩により、消費者購買行動に関する高度な情報がオープンになり、ビジネスパーソンはこれらの情報を活用して戦略を立てるスキルを磨くことができます。データの重要性が理解され、実務で使う情報が広まることで、特定したターゲットに自社資源をぶつけるだけの事例Ⅱは、猫が寝ながら60点と言われるまでの楽勝事例になるでしょう。
デジタルマーケティングにおけるデータドリブンなアプローチが一般的に知られる様になると、ビジネスパーソンはデータを活用してターゲット市場を特定し、新規獲得、販促、反復購入などのステップを効率的に実行できるようになります。これと同様に、診断士事例Ⅱの試験問題も、マーケ実務に詳しい方なら日頃の当たり前以下で正解答案を書けてしまうのです。
③事例Ⅰはそこそこ企業の普段以下
各社の戦略がクローズだった昔と違い、デジタル経済の競争で目指す所は皆同じ。これから点差が付くのは、日頃のセンスとスピードだけになります。
デジタル化が進み、企業の戦略が同質化しています。競合他社との差別化が難しくなり、従来のビジネスモデルが変化しました。都市部のビジネスリーダーなら、この変化に対応するために新たなスキルと知識を既に獲得しており、そのため試験の内容が既知の情報として感じられることがあります。
都市型ビジネス環境では、タテ組織からネットワーク型組織への転換が進み、組織の柔軟性と自由度が高まりました。戦略の立案と実行が迅速に行え、組織内外の連携が効果的です。このため、伝統的な戦略論に基づく診断士試験の事例Ⅰが、彼らにとっては現実のビジネス状況と比較して単純に感じられることがあります
最先端のビジネスプロフェッショナルたちは、タテ型組織からネットワーク型組織への移行に成功し、新しい組織モデルに適応しています。ここ数年の試験の事例Ⅰは、伝統的な組織構造に取り残されたケースを扱うことが多く、都市型ビジネスのリーダーにとっては過去の課題に見えることも、簡単に感じる要因の一つです。
今日のまとめ
試験より世間が定着し今の事例は簡単すぎる
①生成AIを普段使いすると事例が求める以上の答をあっさり書けるが、②当試験の出来すぎ答案は一発退場Dのリスクがあるため、③意識高い答案をどこまで書くかはあなた次第。(100字)
D社のノロマがはしゃぎすぎ、どこが合格ボーダーかは猫にも丸見え。アレより遥か意識の高い答案が書けるのに、ふぞレベルに下げないと受かりにくい。それをイノベーション・ジレンマと呼ぶのです。

