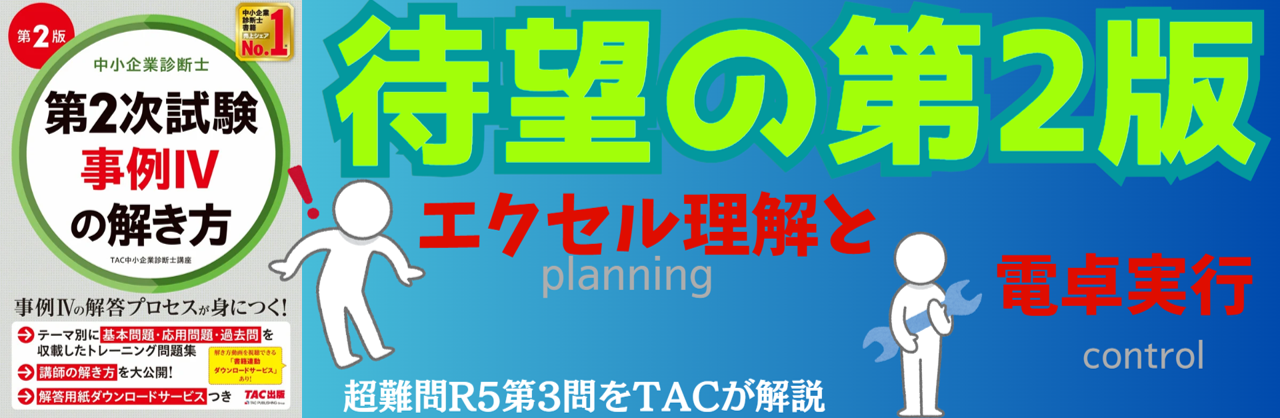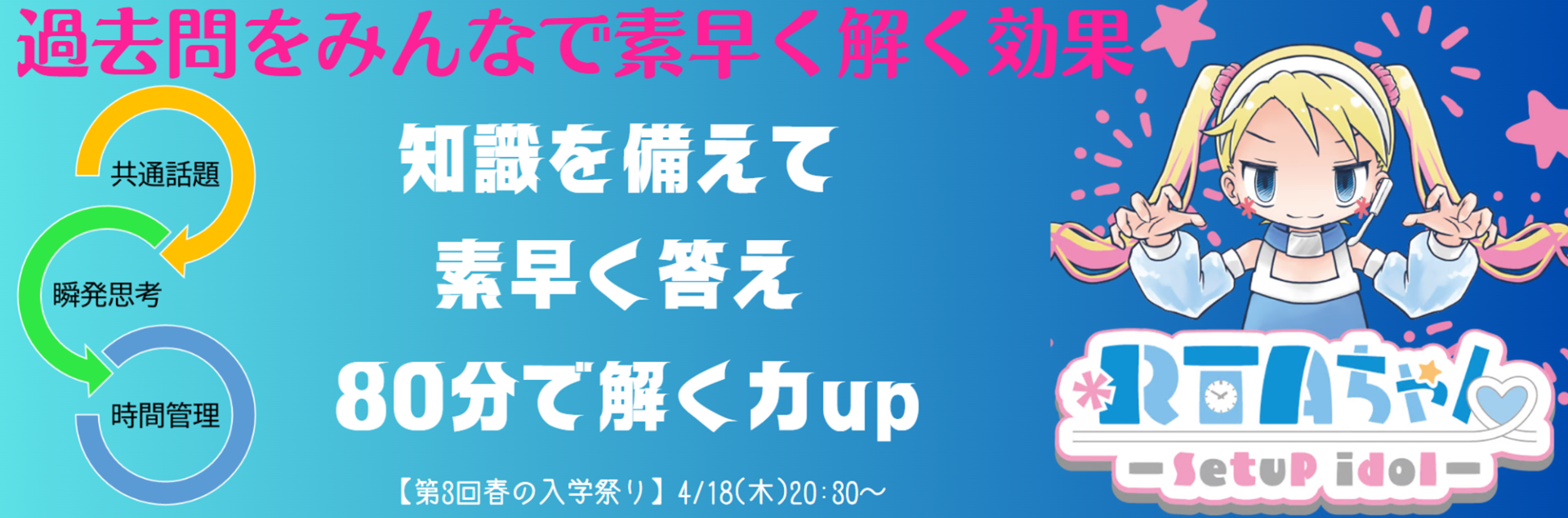R3~4で連続出題された「互恵関係」は、TBCがズバリ正解に。そして二度出た知識を翌年も出すのが当試験です。
中小企業診断士試験で唐突に出題されて話題になった「互恵関係」について教えて。
「互恵関係」とは、企業間の取引において対等な立場で行われる取引関係を指します。
①従来の下請関係や上下関係ではなく、お互いに利益を享受しながら長期的なビジネス関係を構築することが重要視されます。②このような取引においては、お互いに情報共有や技術提供などを行いながら、革新的なアイデアの創出や問題解決が可能となります。③診断士試験では、企業の成長に必要な重要なキーワードとして取り上げられ、出題されたことで注目を集めました。(171字)
【唐突な互恵関係】2年連続事例Ⅰ出題 / 正解したのはTBC / 出典と発展とこれから
2年連続のR4はともかく、初見のR3に「互恵関係」と書くのは9,000人中の山口センセただ1人。ではなぜそうか?の確認な。
近年のネット普及で取引の主役が消費者に移ったことから、事例Ⅰでもマーケ重視の時代とされます。そこで以下3つの点から説明します。
B2Cにおいては、お客様に対して商品やサービスの購入体験を重視し、関係性を構築することが大切です。同様に、B2Bにおいても、単に商品を売り込むのではなく、お互いに信頼関係を築きながらビジネスを行うことが必要です。例えば、長期的な取引パートナーとなることで、互いに利益を生み出し続けることができます。
製品のライフサイクルが短くなっている現代において、企業は製品の開発や製造、販売までを自社ですべて行うことが困難になっています。そのため、外部の企業や専門家に外注することが重要になっています。こうすることで、コストや時間を削減できるだけでなく、専門性の高い業者が担当することで製品の品質や性能も向上する可能性があります。
従来のような下請け関係では、上位企業から下位企業への指示に従うだけの関係になりがちです。しかし、互恵対等な関係になることで、下位企業も積極的にアイデアを出すことができるようになります。例えば、製品の開発において、上位企業と下位企業が協力し合い、お互いにアイデアを出し合うことで、より高品質な製品を開発することができます。
商取引(B2B)上で考える前に、一般的な互恵関係の進め方を紹介します。それはお互いに利益を与え合い、協力し合う良好な関係のことです。
相手のニーズや要望を理解し、その利益を最大化するような方法を考えることが重要です。自分勝手な考え方で行動するのではなく、相手の立場に立った行動を心がけることが必要です。
相手の意見や考え方に敬意を払い、それを尊重することが大切です。また、自分自身も相手に対して尊重されるような言動を心がけることが望ましいです。
相手とのコミュニケーションを頻繁に行い、意思疎通を密にすることが必要です。相手の考えや意見を理解することで、互いの信頼関係が深まり、より良好な関係を構築することができます。
相手に協力し、自分自身も相手からの協力を仰ぐことで、互いに利益を与え合うことができます。このような相互協力によって、より良好な関係を築くことができます。
権威や力、先輩後輩関係をタテに相手に押し付けない。先輩であることが唯一の取柄な某サークルに教えてあげたい知識です。
互恵関係において、互いの力関係を均等にするための手段は以下のようなものがあります。
両社が出資して設立された会社で、事業を共同で行い利益を分け合います。合弁会社により、両社が互いの製品やサービスを補完し合うことで、より強力なビジネスモデルを構築できます。
同等の条件での契約を交わすことで、両社が均等な立場でビジネスを行うことができます。契約内容には、商品やサービスの品質や納期、価格などが含まれます。
技術やノウハウを共有することで、双方が均等な立場でビジネスを行うことができます。技術移転により、両社がそれぞれの得意分野を活かし合うことで、より高度な製品やサービスを提供できます。
共同で研究・開発を行うことで、双方が均等な立場でビジネスを行うことができます。共同研究・開発により、両社がそれぞれの専門分野を活かし合うことで、より革新的な製品やサービスを開発できます。
はい。物量や質量より情報、つまりデジタルなアイデアが勝負になる時代では、以下のようないいコトが起きる可能性があります。
小さな地方企業同士が協力して、地元の資源を活用して新しい製品を開発することで、お互いのビジネスを発展させることができます。また、地元企業と協力して地域のイベントを開催することで、地元住民から支持されるブランド力を築くことができます。例えば、岩手県盛岡市にある株式会社ひろはまと、盛岡冷麺を販売する株式会社松原屋が協力し、盛岡冷麺に合うドレッシングを開発しました。
スタートアップ企業同士が協力して、新しいビジネスモデルを開発することができます。また、異業種の企業同士が協力して、新しい市場を開拓することも可能です。例えば、東京都内にある株式会社エコロジーシステムズと株式会社the oneが協力し、新しい家電製品を開発しました。
複数の小規模企業が協力して、共同で需要の高い製品を生産することで、生産コストを下げ、収益性を向上させることができます。また、複数の企業が協力して、社会問題の解決に取り組むこともできます。例えば、東京都内にある株式会社マルキンと株式会社GADGETSが協力し、リユース可能なショッピングバッグを開発しました。
小さな企業同士が協力して、新しい技術やビジネススキルを学び合うことができます。また、大企業と中小企業が協力することで、大企業のノウハウを中小企業が吸収することも可能です。例えば、福岡県にある株式会社ナカタニと株式会社TENDとが協力し、IT人材の効率的な育成に取り組んでいます。
最初大企業のケースばかり挙げるので、つまらねぇ!と罵ると中小企業白書も顔負けなローカル企業事例がたくさん。この臨機応変さもGPT様の特徴な。
今日のまとめ
そう、訊けばなんでも答えてくれるGPT様。その出典・発展・これからのミライともに、いい感じに当たりそうです。
1930年代にアメリカの社会学者ジョージ・ホーマンによって提唱された社会学理論です。ホーマンは、人々が相手に対して行う行動は、相手からの見返りを期待しているという考え方に基づいて、人間の社会行動を分析しました。
※当サイト注 ジョージ・ホーマンズは実在の社会学者ですが、GPTの主張の真偽は不明です。
その後、ホーマンの理論を基に、経済学やマーケティングなどの分野で、企業間の取引における互恵関係が重要であるという考え方が広がっていきました。そして、2021年には中小企業診断士試験で、互恵関係が出題され、一躍注目を浴びました。
これからも、企業間の取引において、互恵関係が重要であることは変わりません。特に、グローバル化やデジタル化が進む現代においては、企業間の取引がますます複雑化し、互恵関係の重要性が増しています。また、社会的責任を果たすことが企業価値向上につながることも注目されており、互恵関係に基づく取引がますます重要視されることが予想されます。