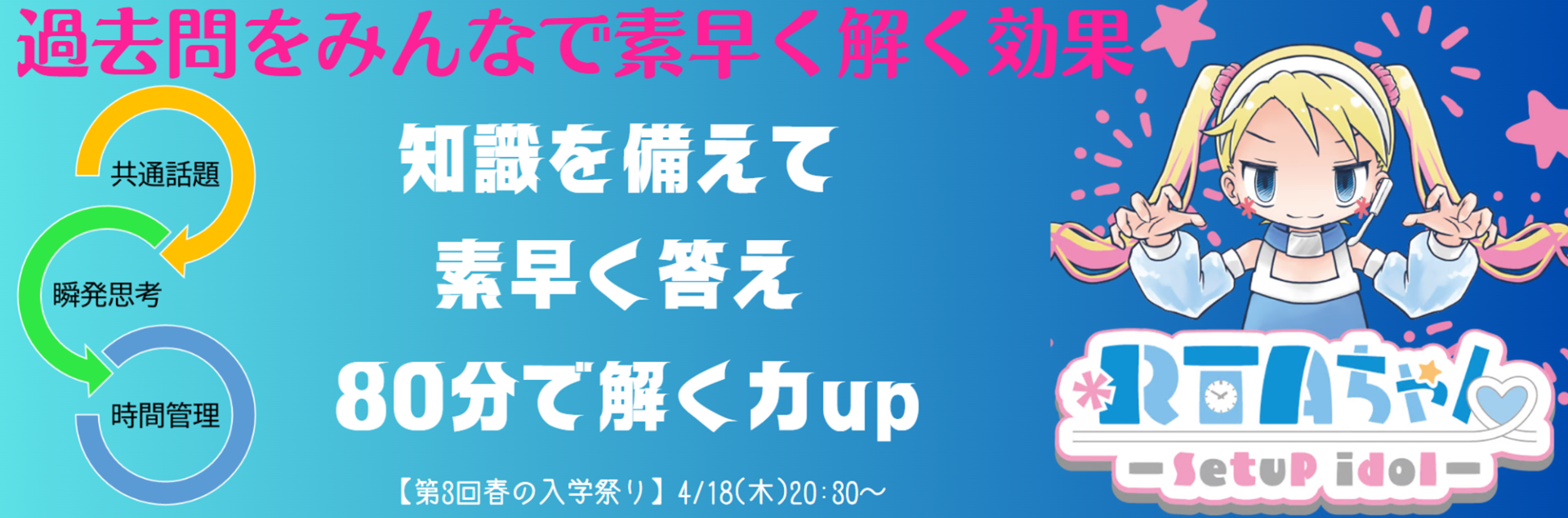初学の猫でも60点を取るⅣで、無意味なお勉強の挙句に余計な自慢で失笑される「イケカコ」。GPT様の力でバッサリ一掃です。
イケカコは古典的な原価計算理論に基づく、高度な専門知識を学ぶための教材です。しかしそれは、わかっていないおベテが答を覚えて頭を固くする被害を生むため、イケカコ禁止3原則を私が考えました。
これ知らないとAI以下~イケカコ禁止3原則
イケカコには解答例があるため、解き方を覚えることに偏りがちですが、事例Ⅳでは、設問の理解と計算での応用を求められます。そのため時間に余裕があれば、イケカコではなく簿記の基礎をしっかりと押さえ、問題の意味を理解することが重要です。
例えば、「1月1日に購入した固定資産の償却費を計算せよ」という問題があった場合、イケカコでは「固定資産:1,000万円、耐用年数:10年、残存価額:0円の場合、1年当たり100万円」という解答例があるかもしれません。しかし、実際の問題では固定資産の種類や耐用年数、残存価額が異なります。そのため、答えを覚えてしまう前に簿記の基礎を身につけ、問題の内容を理解することが大切です。
事例Ⅳで難問が出題されることがありますが、重要なのはその問題を解けたことよりも、問題に対する理論的な説明ができることです。そのため、難問にばかり力を入れるのではなく、問題に対する理論的な説明をしっかりと学ぶことが必要です。
例えば、「法人税の納税義務者は誰か?」という問題があった場合、答えが「法人」となることは簡単に覚えられますが、その理由や法人税に関する詳細な知識を持ち、説明することが求められます。
過去に身に付けた知識やスキルにこだわって、新しい情報や考え方を拒否することで、成長や改善の機会を逃してしまう方をしばしば見かけます。
例えば、昔からやり慣れている方法があったとします。それが正しいと信じ込んでいると、新しい方法や技術に取り入れることができず、業務の効率化や改善ができません。また、同じやり方で何年もやっていると、単純作業化してしまい、いつの間にか必要なスキルや知識を失ってしまう可能性があります。
そのため、常に新しい情報や技術を学び、自分自身や自社の業務を改善するために努力することが重要です。古い自慢を捨てて、新しいことにチャレンジし、成長を続けることが、ビジネスパーソンとして成功するための大切な姿勢です。
【GWはゆるーくslack】イケカコ禁止3原則 / イケてないイケカコ自慢を一掃
イケカコで答を覚えた間抜けがヘタクソ自慢をし、隣がそれをからかう構図。それがわかったあなたのために、イケカコ=NGの理由をいつもの三段論法な。
年1回しかない診断士試験では、難問を解いてお勉強した気にさせるスクールが横行しています。それらのスクールは教材を正しく自作する力がなく、いまだにイケカコでも受かると強調します。
イケカコは、古典的な会計原則に基づく会計理論であり、長年にわたって多くの人々が学んできた伝統的な方法です。この理論は、企業の財務情報を正確かつ信頼性の高い形式で報告することに重点を置いています。
現代のビジネス環境は、多様化し、急速に変化しています。このため、現代のビジネスニーズに適合した会計理論が求められます。例えば、持続可能性や社会的責任など、会計上の問題に対する新しいアプローチが必要とされています。
中小以下の資格スクールでは、既存の教材を流用することで、新しい教育プログラムや教材を開発するコストを削減しようとする動きがあります。そしてイケカコを教材に使用することが多く、現代のビジネスニーズと大きくズレた指導をする点が問題視されています。
イケカコの利点は深い専門知識を必要なだけ学べる点です。一方で、単に難しいうえに解説が不親切で、時流が求めるわかりやすい情報発信力がゼロ以下な所が欠点です。
| 利点 | 補足説明 | 例 |
|---|---|---|
| 古典的な原則に基づく | 古くから存在する会計理論を学び、出題範囲を網羅しやすい。 | イケカコの基本になる原価計算を前提に、それらがどう応用されるかまでの順番を追える。 |
| 出題範囲をカバー | 試験で出題される範囲を学ぶことができる。 | 会計の基本的な知識や原価計算の理論に基づき、NPVまでの範囲に応用できる。 |
| お勉強した気になる | 基本的な会計理論を学ぶことができ、自信を持てる。 | テストで高得点を取ったり試験に受かると、周囲がイケカコを避ける分、変なマウントを取れる。 |
| 欠点 | 補足説明 | 例 |
|---|---|---|
| 複雑なビジネス環境に不適合 | 現代のビジネスニーズに合わない、応用が利かない。 | デジタルマーケティングにおける広告費の管理などは、イケカコより簿記の方が適する。 |
| 解説が不親切 | 何を言っているかが分からない場合すらある。 | イケカコの概念や原則が分からないまま問題を解くと、答えさえ合えば良いとなりがち。 |
| 解き方を覚えて応用が利かない | 応用が利かないため、実務に向かない。 | イケカコの問題を覚えて解くことはできても、多くの場合、それをビジネスに活かすことができない。 |
はい。まず簿記知識は不要の前提で、試験に事例Ⅳが設置されている狙いを考えます。そこでは財務諸表の読み方や利益計画・投資計画の妥当性を、中小企業の経営者に、わかりやすく説明するスキルが求められています。
事例Ⅳの60点には、企業診断に必要な会計知識を全て理解している必要はありません。代わりに、中小企業の現状把握や経営分析に必要な基本的な考え方を理解しましょう。簿記に関する知識がない人でも、財務諸表を読み解く能力や、収益性や資産管理、キャッシュフローの観点から会社を分析し、中小企業経営に貢献することができる。そこを前提にすると、事例Ⅳの捉え方が明確になります。
お受験ベテが珍重するイケカコは、試験合格に必要な知識の一部に過ぎません。診断士試験では、財務諸表の作成や分析、経営計画の策定や評価、業務改善の提言など多岐にわたるスキルや知識が求められます。イケカコを使わなくても、試験に出題される問題を解決するために必要な知識や技能を身につける手段が他にあります。
同じくイケカコは、試験合格への十分条件にもなりません。中小企業診断士を名乗るためには、業務に必要な知識やスキル、実践的な能力を身につける必要があります。そこで難問の解き方を覚えることよりも、試験で出題される問題に対して、その場で適切な判断を行い、解決策を提示できるスキルの方が大切になります。
今日のまとめ
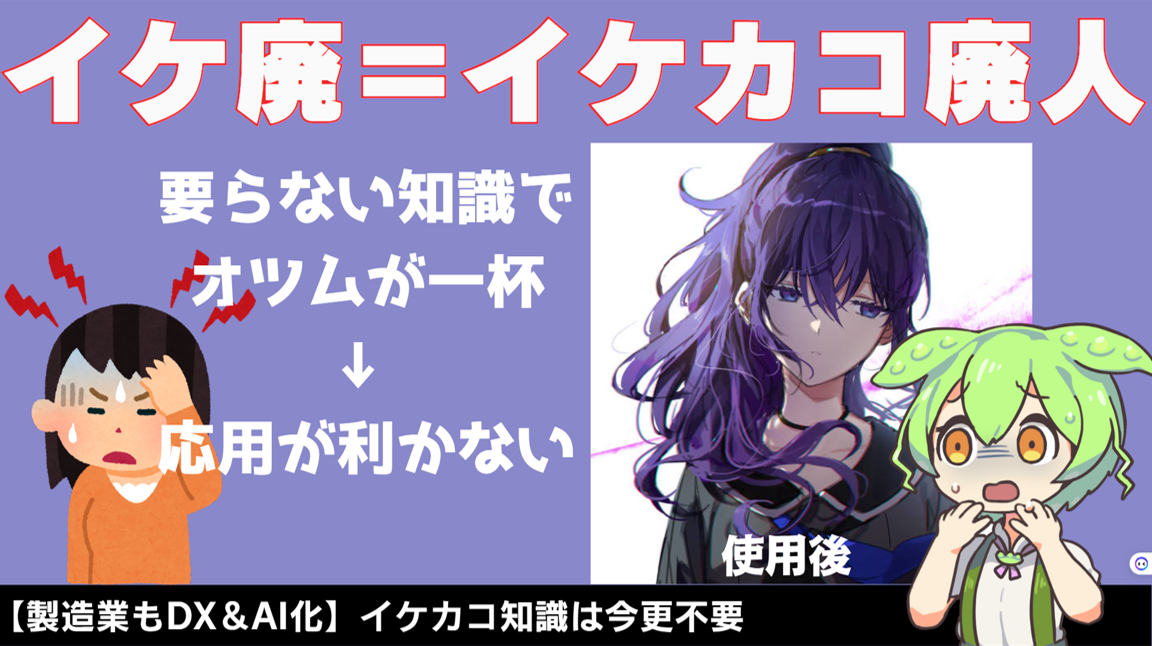
イケカコはⅣ60点の必要条件でも十分条件でもなく、かつ実務での使い道もゼロ以下。そこに余分に掛けた合格コストを自慢を通じて回収する行為は、診断士として感心しません。